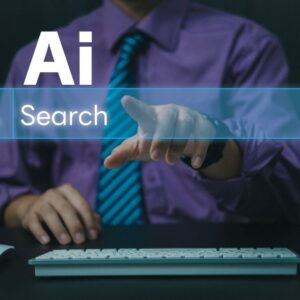アドラー心理学が教えてくれた「劣等感」を乗り越え「自分軸」で生きる道


下記の記事をラジオ番組風にNotebookLMで音声に変換しました。
毎日の片道40分、電車に揺られながらAudibleで小泉健一さんの『今さらだけどアドラー心理学を実践してみたらすごかった!』を聴くのが、最近の私の日課です。通勤時間をただの移動時間ではなく、自己成長の貴重な時間に変えてくれるこの習慣は、私にとってかけがえのないものになっています。特に心に響いたのは、「自分を肯定することの大切さ」と「他人軸ではなく自分軸で生きること」というアドラー心理学の教えでした。そして今回、さらに深く私の心に刺さったのが、「縦の関係」と「横の関係」という人間関係の視点です。これらの教えが、長年抱えていた私の心のモヤモヤを晴らす光となり、新たな視点を与えてくれたのです。
劣等感との長い付き合いと、一筋の光
私の幼少期は、常に兄との比較の中にありました。「おまえは兄に比べて…」という言葉は、まるで呪文のように私の心に劣等感を深く植え付けました。漢字の書き取り宿題は母にやってもらい、私は遊びに出かける。そんな体たらくで、国語の成績はいつも芳しくありませんでした。この幼少期に植え付けられた劣等感は、まるで頑固な染みのように、なかなか拭い去ることができませんでした。
しかし、中学に入学し、ある先生との出会いが私の人生を大きく変えることになります。数学の女性教師は、私が兄と比較されてきたことを知ってか知らずか、「お兄さんができるんだから、あなたもできるわよ」と、常に私を肯定する言葉を投げかけてくれました。彼女の言葉は、それまでの「できない自分」という固定観念を打ち破り、「もしかしたら自分にもできるかもしれない」という希望の光を灯してくれたのです。
この先生との出会いを境に、私の内面に大きな変革が起こりました。彼女の励ましのおかげで、数学はいつもトップクラスの成績を収めるようになり、その自信が他の教科にも波及し、徐々に全体的な成績も向上していきました。ただ、唯一、国語だけは相変わらず苦手なままで、ここにも幼少期の劣等感の根深さを感じさせられます。それでも、あの時の先生の言葉が、私を劣等感の淵から救い出し、自己肯定への道を歩み始めるきっかけとなったことは間違いありません。
アドラー心理学が示す「自分軸」という生き方
アドラー心理学から学んだもう一つの、そして非常に感銘を受けた考え方があります。それは、「一つの出来事を他人軸と自分軸に分けて考える」という視点です。これは、私自身の長年の悩みに明確な答えを与えてくれるものでした。
私たちはとかく、他人の言動や状況に感情に左右されがちです。仕事で同僚がやるべきことをやらない、期待通りの成果を出さないといったことに腹を立て、ストレスを溜めてしまうことは少なくありません。私自身も、まさにそうでした。他人がやらないことにイライラし、それが自分のストレスとなり、さらには生産性の低下にもつながっている。そんな悪循環に陥っていることに、アドラー心理学を通して気づかされたのです。
アドラー心理学は、「他人の領域に入って他人がしないことを自分が悩んでも仕方がないこと」だと教えてくれます。そして、「自分を変えることができるのは自分だけだから、自分のことを精一杯やることに集中することが大切だ」と説きます。この考え方は、私の心に深く響きました。
「課題の分離」で心の平穏を手に入れる
この「他人軸と自分軸」という考え方は、アドラー心理学でいう「課題の分離」という概念に繋がります。簡単に言えば、「これは誰の課題なのか?」と問いかけ、その課題が自分のものであれば対処し、他人のであれば干渉しない、というものです。
例えば、私が仕事で他人がやらないことに腹を立てていた状況を「課題の分離」に当てはめてみましょう。
他人が仕事をしない:これは「他人の課題」です。私がどれだけ心配したり、怒ったりしても、その人が行動を変えるかどうかは、その人自身の選択に委ねられています。私がコントロールできることではありません。
他人の行動によって私がストレスを感じる:これは「私の課題」です。他人の行動は変えられなくても、それに対する私の感情や反応は、私が変えることができます。
この区別をすることで、私は不必要な感情的な負担から解放されることができるのです。他人の行動に一喜一憂するのではなく、「自分にできること」に焦点を当てる。具体的には、自分の仕事に集中し、自分の責任範囲を全うする。必要であれば、建設的な提案はするものの、最終的な行動は相手に委ねる。この意識を持つことで、これまで他人の問題に費やしていたエネルギーを、自分の成長や仕事の質を高めることに使うことができるようになりました。
人間関係を解き放つ「縦の関係」と「横の関係」
そして、今回最も心を揺さぶられたのが、アドラーが提唱する人間関係における「縦の関係」と「横の関係」という視点です。これは、私たちの日常生活に潜む多くの衝突や不満の根源を明らかにし、より良い関係性を築くための羅針盤となる考え方です。
私たちは無意識のうちに、人間関係を「縦の関係」として捉えがちです。まるでピラミッドのように、親と子、上司と部下、夫婦といった関係を「主従関係」として見てしまうのです。この視点に立つと、上の立場の者が下の者を権限で従わせようとし、そこに反感や衝突が生まれてしまいます。
例えば、子供が親の言うことを聞かない時、つい私たちは「親の言うことを聞きなさい!」と、力でねじ伏せようとする言葉や態度を取ってしまいませんか? 夫婦関係でも、夫が妻に「俺が稼いでいるんだから」といった上から目線の言葉を投げかけ、夫婦間にギクシャクした空気が流れた経験はないでしょうか。これらの関係性は、まさに「縦の関係」がもたらす摩擦の典型です。相手を対等な存在として見ず、自分の権限や立場を振りかざすことで、心の距離が生まれ、信頼関係が損なわれてしまうのです。
しかし、アドラーは、真に健全な人間関係を築くためには、「横の関係」を築くことが大切だと教えています。これは、対等な立場、つまり「ともだち」や「仲間」としての意識で人と接するという考え方です。
例えば、職場において、上司と部下であっても、互いを尊重し、対等な言葉や態度で思いやりを持って接すること。それは、まるで旧知の友人のように、互いの意見に耳を傾け、協力し合える関係を築くことにつながります。上司だからといって一方的に命令するのではなく、部下の意見にも耳を傾け、共に目標達成を目指す。部下もまた、上司を単なる権力者としてではなく、同じ目標に向かう「仲間」として認識する。このように「横の関係」を築くことで、職場の雰囲気は劇的に改善し、生産性も向上するでしょう。
夫婦関係も同様です。どちらが上でどちらが下という支配的な関係ではなく、お互いが「人生を共に歩む仲間」として、家庭という共同体を築き上げている意識を持つことです。家事や育児の分担、将来設計など、あらゆることについて対等な立場で話し合い、協力し合う。そこに優劣の意識がなくなれば、夫婦間の衝突はぐっと減り、互いをより深く尊重し合える関係が生まれます。
そして、親子関係においても「横の関係」は非常に有効です。子供を単に「未熟な存在」として扱うのではなく、一人の人間として尊重し、友達のように何でも話せる関係を築くことができれば、子供の反発は少なくなるのではないでしょうか。もちろん、親としての責任や指導は必要ですが、それは「支配」ではなく「援助」の視点から行われるべきです。子供の意見にも耳を傾け、共に考え、成長をサポートする。そうすることで、子供は安心感を持ち、自律性を育んでいくことができます。
「劣等感」は「成長の原動力」となる
アドラーは、劣等感そのものは悪いものではないと考えています。むしろ、劣等感は「より良く生きよう」「成長しよう」という欲求の源泉になると説いています。私の幼少期の劣等感も、数学の先生との出会いを経て、数学の成績向上、さらには他の教科への意欲へと繋がっていったように、形を変えて私の成長の原動力になっていたのかもしれません。
重要なのは、劣等感を「優越性の追求」へと繋げることです。これは他人と比較して優位に立つことではなく、「理想の自分」に向かって努力し、自己を高めていくことを意味します。私にとっての「優越性の追求」は、数学でトップクラスを目指すこと、そして今、アドラー心理学を学び、自己肯定感を高め、自分軸で生きることを目指すことなのかもしれません。
自分を肯定することの絶大な力
Audibleでアドラー心理学を聴き、改めて強く感じたのは、「自分を肯定することの絶大な力」です。幼少期に植え付けられた「おまえは兄に比べて…」という言葉は、私の自己肯定感を深く傷つけました。しかし、中学の数学の先生が投げかけてくれた「お兄さんができるんだから、あなたもできるわよ」という肯定の言葉が、私の凝り固まった心を解き放ち、新たな可能性を示してくれました。
私たちは、他人からの評価や過去の経験によって、自分自身を過小評価しがちです。しかし、アドラー心理学は、「過去が現在を決定するのではない」と教えてくれます。過去にどんな経験があろうとも、私たちは「今ここ」で、未来に向けてどう生きるかを選択することができます。そして、その選択の第一歩は、「自分自身を信じ、肯定すること」から始まるのです。
私自身、国語の苦手意識はまだ残っていますが、それも「できない自分」と決めつけるのではなく、「まだ伸びしろがある自分」と捉え直すことができるようになりました。完璧でなくてもいい。少しずつ、自分のできることを増やしていく。そのプロセスそのものが、自己肯定感を育む大切なステップなのだと理解できるようになりました。
「今」を生き、「自分」を生きる
アドラー心理学は、私たちに「今、ここを生きる」ことの重要性を説きます。過去の後悔や未来への不安に囚われるのではなく、「今、自分にできること」に集中する。そして、他人の期待や評価に振り回されることなく、「自分自身の価値基準」で生きる。
この視点を持つことで、私の心には大きな変化が訪れました。他人の行動にイライラしたり、過去の自分を責めたりする時間が減り、その分、自分の仕事やプライベートの充実に意識を向けられるようになったのです。
もちろん、実践は容易ではありません。長年の思考の癖はすぐに変えられるものではないでしょう。それでも、通勤時間にアドラーの教えを耳にするたびに、その意識を再確認し、少しずつ実践していくことで、確実に私の日常は変わり始めています。
まとめ
アドラー心理学は、私に以下の大切なことを教えてくれました。
劣等感は成長の原動力: 劣等感は克服すべきものではなく、より良い自分を目指すためのエネルギーとなる。
自己肯定感の重要性: 他者からの肯定だけでなく、自分自身を信じ、肯定することが、人生を豊かにする第一歩。
課題の分離: 他人の課題に干渉せず、自分の課題に集中することで、心の平穏と自由を手に入れる。
縦の関係から横の関係へ: 親子、上司と部下、夫婦といったあらゆる人間関係において、支配ではなく協力と尊重に基づいた対等な関係を築くことで、真の絆と調和が生まれる。
自分軸で生きる: 他人の評価に囚われず、自分自身の価値観で「今、ここ」を生きる。
これらの教えは、私の長年の悩みを解消し、より建設的で前向きな思考へと導いてくれました。まだまだ道半ばですが、アドラー心理学を羅針盤として、これからも「自分らしく」、そして「幸福に」生きる道を歩んでいきたいと思います。
あなたももし、私と同じように過去の経験や他人の評価に囚われがちだと感じるなら、ぜひ一度、アドラー心理学に触れてみてはいかがでしょうか。きっと、あなたの心にも新たな光が差し込むはずです。